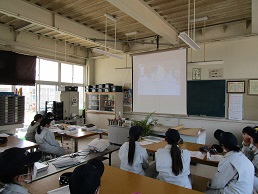岡山家畜保健衛生所の先生方に、牛結核病の診断について教わりました。牛結核病の診断には人間と同様でツベルクリン反応検査で行います。3日前にツベルクリンを接種し、尾の根元の腫れ具合で診断を行います。本校の牛は全頭陰性でした。最近では数十万頭の検査で1頭が陽性となるレベルまで清浄化が進んでいる病気です。

続けて、受精卵を移植した牛の妊娠鑑定も行いました。受精卵移植とは、受精した母牛から受精卵を採取し別の母牛に移植して妊娠させるという技術です。 3月に実施した母牛が妊娠しているかをエコー検査で鑑定していただきました。「しんひでなみ号」は無事に親指サイズの胎児を確認することができました。安定期となる60日頃までは流産しないよう慎重に管理を行っていきます。