今日は、園芸科学科野菜類系の3年生が育てている水耕栽培メロン(アールス系)です。
3月はじめに種をまき、3月終わりに定植したメロンも気温の上昇とともに成長してきました。草丈は生徒の調査で50センチ~70センチ位になっています。
最近の管理として、必要のない花、ひげづる、液芽を取り、誘引ひもにクリップで誘引をしています。これは、狭い場所でたくさんのメロンを栽培するためにするものです(立体栽培ともいいます)



ああああ順調にいけば5月の連休明けに人工授粉をし、7月に収穫をすることが出来ます。頑張って管理しましょう。






































































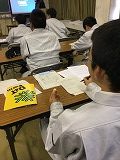
 →
→ 















