8月26日(火)、岡山市立上道公民館で、小学生を対象に料理教室を行いました。家庭クラブ役員8名が、小学生14名に作り方を師範しながら、一緒に作りました。
メニューは「夏野菜たっぷりそうめんチャンプルー」「ポテトサラダ」「フルーツポンチ」です。「フルーツポンチ」には、瀬戸南高校産のマスカットと桃を使いました。甘く、とても好評でした。
試食の時には、家庭クラブ役員から、「野菜を残さず食べてほしい。」との思いから、紙芝居を使って野菜についてのクイズをしました。子どもたちは、苦手な野菜も残さず、仲良く食べてくれました。
また来年も、小学生に喜んでもらえる企画をしたいと思います。


















 今日は最後の体側です。体重と中足骨長を測定します。チャンキーブロイラーの飼育は終了です。生物生産科2年生飼育類型が全員集合しての実習です。
今日は最後の体側です。体重と中足骨長を測定します。チャンキーブロイラーの飼育は終了です。生物生産科2年生飼育類型が全員集合しての実習です。






 私たちは、岡山市の長谷井商店に見学研修に行ってきました。
私たちは、岡山市の長谷井商店に見学研修に行ってきました。


 長谷井商店の皆様、説明してくださった井上さんありがとうございました。
長谷井商店の皆様、説明してくださった井上さんありがとうございました。




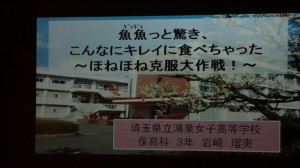
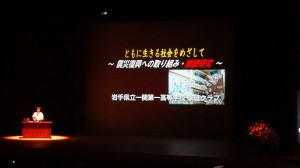



















 次の9月の新人戦に向け、また練習に励みますので、応援よろしくお願いいたします。
次の9月の新人戦に向け、また練習に励みますので、応援よろしくお願いいたします。














 市(いち)の前日の午後4時に真庭市の家畜市場に運んでもらう為に、牛運搬用のトラックで学校から運搬のプロに運んでもらいます。牛さん、家畜市場でまた合いましょう。
市(いち)の前日の午後4時に真庭市の家畜市場に運んでもらう為に、牛運搬用のトラックで学校から運搬のプロに運んでもらいます。牛さん、家畜市場でまた合いましょう。




 セリ値は、49万5千円????????
セリ値は、49万5千円????????