4月25日(土)9時30分より本校農場にて、「第10回春の苗物販売会」を開催いたします。
野菜苗、草花苗、卵、ローストチキン、米などの生産物を販売予定です。(詳しくは、ページ下のデジタルチラシをご覧下さい。)
生産物はもちろん、テントなど会場準備も着々と行っています。









oniビジョンさんが取材に来て下さいました。園芸科学科の3年生が出演しました。



当日、快晴の場合、気温が高くなる可能性があります。熱中症対策として水分補給などの体調管理をお願いします。
4月25日(土)9時30分より本校農場にて、「第10回春の苗物販売会」を開催いたします。
野菜苗、草花苗、卵、ローストチキン、米などの生産物を販売予定です。(詳しくは、ページ下のデジタルチラシをご覧下さい。)
生産物はもちろん、テントなど会場準備も着々と行っています。









oniビジョンさんが取材に来て下さいました。園芸科学科の3年生が出演しました。



当日、快晴の場合、気温が高くなる可能性があります。熱中症対策として水分補給などの体調管理をお願いします。
4月に入り、3月初めに種まきしたメロンが定植するのに良い時期がきたので、苗を水耕栽培ベッドへ植えました。生徒達は苗から出ている根へ顔を近づけると、ほのかにメロンの香りがしたようで、嬉しそうに苗を植えていました。これから、5月に人工交配をして7月中旬ぐらいの収穫を目指して栽培します。
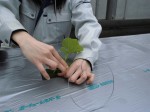


1月の終わりに種まきした大玉トマトの苗を定植する時期をむかえました。種まきから約2ヶ月の間、肥料まき、畝作り、誘引パイプの設置などの作業をしてきました。定植後も管理を続け、早ければ5月の終わり頃から、おいしい真っ赤なトマトを収穫する予定です。生徒達も楽しく実習しています。





園芸科学科草花類型の春期休業中の当番実習の様子です。
だんだんと暖かい日が多くなってきて、花壇の花々の隙間からの雑草が目立つようになったので、創立90周年を迎える新年度に向け、中庭の装飾も兼ねて、農業棟の教室前にある花壇の手入れをしました。
リュウノヒゲやパンジー、ビオラの隙間から顔を出す雑草を丁寧に取り除きました。



またプランター用土の消毒をし、袋詰めを行いました。スコップを持つ手が少々ぎこちないですが、2人1組で協力しながら行いました。この土は、H28年度インターハイ用装飾プランターの試験栽培(H27年度)に使われます。



暖かい気候となり、生物生産科の畜産部では動物たちの出産が続いています。かわいらしい子ウシ、子ヤギがどんどん誕生しています。子ウシたちは母親のお乳をたっぷり飲み、すくすくと育っています。毎日、飼育類型や動物飼育同好会の生徒たちが愛情を注いで管理しています。




春のような日ざしの中、今日は1号水田に堆肥を散布しました。使用する作業機は「マニュアスプレッダ(堆肥散布機)」。トラクタの後ろに牽引(けいいん)して使用します。2年生はマニュアスプレッダの操作は初めてなので、説明をしっかりと聞いて、事故の無いように作業を進めました。
マニュアスプレッダの入れない水田の隅は、手で散布しました。





本日、生徒と一緒にシクラメン祭りで販売する下仁田ネギを畑へ定植しました。

白いネギの部分を作るために溝を掘りあげ、苗を3cmから5cmの間隔で置き、軽く覆土をします。その後、ワラを置いて作業は終了です。
今後、数回土寄せをして軟白部(ネギの白い部分)を増やしていきます。
美味しく育ちますように!!
3月4日(水)生活デザイン科1年生が「生活産業基礎」の授業の一環として、岡山市北区にある、平林金属株式会社リサイクルファーム御津に見学に行きました。
2001年に施行された「家電リサイクル法」に基づく、家電リサイクルの仕組みについて分かりやすく説明していただいた後、実際に家電製品4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)がリサイクルされる様子を見学しました。
以下、生徒の感想の一部を紹介します。
○私が一番印象に残っているのは、手作業が多かったことです。機械を使うことばかりだろうと思っていましたが、1つ1つ部品を外したり分けたりするのは大変だなと思いました。
○「限られた資源を、最大限有効に活かして使う」という言葉をお聞きして、本当に大切なことだなと思いました。リサイクル工場では、ただ分解するだけではなく、地球に配慮しているところが素晴らしいと思いました。私も家でできる分別をしていきたいです。

3月3日(火)・4日(水)の2日間の日程で、日本赤十字社岡山県支部から2名の講師をお招きし、幼児安全法の講習会を行いました。


2月18日(木)に、備前市を拠点に活動をしておられる「かばくんクラブ」のみなさんをお迎えし、人形劇講習会を開催しました。
手遊び、読み聞かせ、パネルシアター、ボードビルなど盛りだくさんの内容を実演していただいたあと、グループに分かれてのワークショップを御指導いただき、最後はお互いに発表し合いました。

3月10日、だんだん暖かい日が増えてきていましたが、久しぶりに雪が舞いました。
短時間でしたが、かなりの雪が舞いました。その中、実習の手を止めること無く育雛器(いくすうき:ヒヨコを育てる器械)の洗浄をしている生徒、実習に果樹園へ向かう生徒などを見かけました。
また、屋根はあるけど、外で実習を行っていたり、部活をしていたり、悪天候に負けない生徒の姿に誇らしさを感じました。昼食時間にも激しく降ったので、帰宅する生徒や職員室に戻る教員にも容赦なく雪にまみれました。もちろん本校の牛の背にも雪が積もりました。









3月7日、半田山植物園にてクリスマスローズ協会のイベントに草花類型シクラメン班の5名が参加しました。平成22年度から半田山植物園の一角にクリスマスローズと原種シクラメンのコラボ定植をさせていただいています。今回も観察会と調査をかねて参加でき、特別に園芸研究家の横山直樹氏が来園されていて、午後からは岡山国際交流センターにて同氏の講演会に参加しました。雨の中での観察会になりましたが、クリスマスローズ協会とコラボができて気持ちは晴々でした。






栽培類型の1・2年生がジャガイモの種芋を植え付けました。品種はデジマです。
水田に畝(うね)を立て、大きさに合わせて種芋を切り分け 、30cm間隔で植え付けました。田植えが始まる前の6月上旬に収穫予定です。





3月4日、新年度に向けモモの管理作業も本格的に始まりました。まだまだ寒い日が続いていますが、日増しに春の訪れが感じられ、新芽も勢いよく芽吹いていました。今回の実習では新2年生が担当するゴールデンピーチの摘雷(てきらい:不要な花のつぼみを取り除く作業)を行いました。1年生は1月から果樹・野菜・草花の3類型に別れての実習になっています。果樹類型を専攻した生徒達は、まだまだ作業に慣れないようで悪戦苦闘しながらも一生懸命の姿が伝わってきます。
2年後には最高学年としてモモ園を管理する責任者として実習に臨めるように指導していきたいと思います。


マリーゴールドとサルビアが発芽後順調に育ってきたので、セルトレイからポットに移植しました。1株ずつ丁寧にポット上げを行いました。これからも引き続き良い苗に育つように管理していきます。マリーゴールドは黄・オレンジ・赤など、サルビアは赤・青・白・ピンクなどの花が咲く予定です。春の苗物販売会には、きっと可憐な花を咲かせはじめていることでしょう。






園芸科学科 草花類型の1・2年生(48名)が協力して、卒業式用のコサージを作製しました。
1ヶ月前からコサージリボンの練習を始め、3日前にリボンの準備ができました。
2日前から花材を切り分けたり、ワイヤリング(花に針金を通して補強する)をしたりして下準備しました。
卒業式予行の後、午後から花材を組み合わせて、リボンをつけ作製しました。
今年の花材は、シンビジウム、カーネーション、カスミソウ、ミリオングラタス、レザーファンで、2年生が、1年生に作り方を指導しました。
卒業式の朝、3年生の教室まで行き、緊張しながら149名の卒業生の胸にコサージを付けました。
在校生からの思いが込められたコサージを胸に、心の温まる卒業式が行われました。








2月27日、生物生産科3年の飼育類型16名と先生方が参加して、卒業式前に畜魂慰霊祭を行いました。学習のため多くの尊い家畜たちの命をいただきました。校内に設置されている畜魂碑に、代表生徒が家畜たちへの思いと、卒業後の自分達の進むべく方向を誓いました。最後に、花をたむけ、「命の教育」が完成しました。



生物生産科栽培類型2年生が、除草のために菜の花を栽培してお米を生産している農家の見学に出かけました。今年、実際に自分たちで栽培した経験と比較しながら、菜の花にも連作障害があること、同じ役割でレンゲやヘアリーベッチなどのマメ科作物も利用できること、収穫量は反あたり8俵であるが売り方で十分に利益が出ることなど、興味深いお話をたくさん伺うことができました。また、自分で改造された耕耘機や、高品質なお米を出荷するために工夫されている選別機なども見せていただきました。
来年に向け、1年生が菜の花の播種をしました。しっかりと引き継いでいきたいと思います。
お忙しい中、お時間を割いてくださりありがとうございました。



米、米麹菌、大豆、塩、水だけで作る、人工添加物ゼロで大好評の瀬戸南の米味噌ですが、来年度分の仕込みが終わりました。
生物生産科栽培類型の冬の大仕事です。
1日目はお米の準備、2日目は米麹作り、3日目は米麹の手入れと大豆の準備、4日目は米麹の塩切りと大豆との仕込みです。各工程を理解しながら、衛生面に気をつけ、瀬戸南伝統の味の継承を行っています。








2月19日(木)、園芸科学科果樹類型2年生を対象にモモのせん定講習会が行われました。東備農業普及指導センターより2名の講師の方々が来られ、「モモの仕立て方」や「開心自然形」を構成する枝の名称などについて学習しました。「実際にせん定しようとするとどれを切っていいのか戸惑ってしまう」、「早く覚えて1人で管理できるようになりたい」と意気込んでいる生徒もおり、今後の実習に期待が膨らみます。


