園芸科学科1年生がビニルハウスへ栽培する大玉トマトの肥料をまきました。はじめになぜ肥料は必要なのか、そして肥料はどれぐらいの量が必要なのか計算方法も学びました。生徒も肥料をまく実習は初めてで慎重にまいていました。また、先週まいたトマトの観察やスケッチ、発芽率を求めました。
野菜を栽培するためのいろいろなことを学んでいきます。少しでも自分で育てた!といえるよう頑張って欲しいです。






園芸科学科1年生がビニルハウスへ栽培する大玉トマトの肥料をまきました。はじめになぜ肥料は必要なのか、そして肥料はどれぐらいの量が必要なのか計算方法も学びました。生徒も肥料をまく実習は初めてで慎重にまいていました。また、先週まいたトマトの観察やスケッチ、発芽率を求めました。
野菜を栽培するためのいろいろなことを学んでいきます。少しでも自分で育てた!といえるよう頑張って欲しいです。






園芸科学科草花類型の2年生は、「儲かる農業」「攻めの農業」を実践するため、自分たちが育てたミニバラをプリザーブドフラワーに加工する模擬会社を起業し、活動してきました。2月8日、株主として出資してくださった先生方、保護者の方をお迎えし、株主総会を開催しました。予想される質問に答えられるように万全の準備をして臨んだのですが、先生方からの鋭い質問にタジタジな場面も・・・。しかし、最後までひるむことなく、立派に総会を終えることができました。終わった後の感想は、「疲れた・・・。」でした。



スライドで事業報告 株主から鋭い質問! 社員が立派に答弁!
無事に黒字経営で終えることができましたので、出資金をお返しし、配当の草花苗をお渡ししました。株主の皆様、ご協力ありがとうございました。そして社員のみなさん、お疲れ様でした。
2月5日(火)、ホテルグランヴィア岡山にて、テーブルマナーについて教わりました。
実際にフルコース料理を目の前にすると緊張してしまいましたが、事前に学習していた内容をお互いに確認し合いながら、また一つ一つの作法を教えていただきながら、おいしい料理を楽しみました。講習会後は、ホテル内の施設を案内していただきました。ドレス製作を経験した生徒たちは本物のウエディングドレスに大興奮でした。
今日学んだことをきちんと身につけ、卒業後は社会人として立派に生活していってくれると信じています。





1月25日(木)・2月2日(木)の2日にわたり、つぼみ咲くプロジェクトより森日和先生をお招きし、礼儀作法や日本のしきたりについての講習会を行いました。
1日目には「語先後礼」と「五節句」について、2日目には「箸の作法」と「二十四節気」について学びました。どの作法でも相手を敬う気持ちを表すことができること、当たり前に感じている日々のしきたりにもすべてに背景や理由があることを知ることができました。今回学んだことを、普段の生活や今後の実習などにしっかりと生かしていきます。




園芸科学科1年生が来年度の栽培学習の教材となる大玉トマトのたねをまきました。
品種は麗夏といいます。
今回は、たねまきをするまでにどんな作業をするのか行程も学びました。
たねをまく土はどんなものがよいか、土の水分量はどれぐらいかよいがよいか、たねの上にかける土の量はどれぐらいがよいのかなど、一斉に発芽させるためのポイントを学びました。
生徒たちも自分たちで管理する野菜なのでよく集中して聴き、実習をしていました。
次回はポットに鉢上げをする予定です。頑張って皆で管理しましょう。








今回は、来年度(H30)用の野菜苗をつくる準備をしました。
野菜苗はたねをまくだけでは出来ません。お店で売っているような苗にするためには苗土が必要になります。
苗土をつくるために、土に数種類の資材を機械で混ぜあわせました。また寒い時期にたねをまけるように、暖かくするための温床線を苗床に敷きました。
温床線暖房の仕組みと必要な理由を学び、野菜苗はたねをまくだけでは出来ないことを理解した時間でした。




節分を前に「農業と環境」という科目で「節分アレンジメント」を作りました。
2.5号ポットに12cm角のセロハン、1/8オアシスを入れ花器を作ります。花材類はソテツ8本(7cm大)、オタフクナンテン10本程度(10cm大)、カスミソウ3本(8cm大)、シクラメンの花5本(7cm大)です。
「魔除け」の意味を持つヒイラギの代わりにソテツを使いました。葉先は針のようで危ないため、平たく切り、八方向にさしました。
オタフクナンテンは「難を転ずる意味」です。オアシスが見えないように10本の角度を変えてさしました。
カスミソウはフラワーアレンジメントの脇役で、「清らかな心」「親切」という花言葉を持ちます。
最後にシクラメン。瀬戸南高校で力を入れて栽培している花です。温室ではまだきれいに咲いています。これらを使いできたものがこれです。涼しい玄関では、これから約2週間、花持ちをします。
オリジナルのアレンジメントを楽しみました。1年B組は2月2日です。



園芸科学科2年生が今月、課題研究の発表を行いました。2年生も聴衆者として参加しました。
発表内容はブドウの着色向上や栽培方法の違いによる生産量、暑さに弱い品種の栽培方法の研究など様々な発表が見られました。
研究は2年生の3学期頃から始めた生徒もいますので一年間かけた発表といえると思います。発表態度はさすが3年生でした。
2年も思いを受け止めてくれたと思います。しっかりとバトンをつなげられた発表会でした。




9時から11時30分まで南古都の在宅介護支援センター「古都の森」でクリスマス会に参加しました。
60円のパンジー・ビオラのポット苗や500円のシクラメン鉢まで様々なものを準備しました。たねから丹精を込めて栽培してきたものが売れていくのはうれしいけれど、少しさみしさも感じました。買ってくださった方のところで、元気に咲き続けてほしいと強く思いました。



~去年のシクラメン、今年も咲かそう その5~というテーマの下、今年最後のシクラメン講座を開きました。
今回は、「開花状態の観察・反省評価」です。参加された10名の方と大切な数年越しのシクラメンを持ち寄り、状況の伝達会を行いました。花の形が珍しいシクラメンとの交配実験も行いました。そして、クリスマスが近いのでプレゼント交換をしました。
講師役を務めた3年生が1分間スピーチの中で自分の進路先を報告すると、拍手が起こり、照れくさそうにしていました。
最後はお決まりの記念撮影で結びました。


1月24日(水)に生活デザイン科の1年生を対象に、「フードデザイン」の授業に外部講師として、「政木クッキングスクール」校長の政木信昭先生にお越しいただき、調理技術の基礎について講義と実習の指導をしていただきました。
ご飯の水加減や野菜の切り方、だしの取り方など、基礎からしっかり学び、「豚肉の焼売、沢煮椀、ほうれん草のごま和え」を作りました。沢煮椀は野菜を丁寧にせん切りにし、昆布とかつおで取っただしで作り、優しい味に仕上がりました。手作り焼売(シュウマイ)は本当においしくて、家族にもまた作ってあげたいと思いました。
外部講師の先生によるフードデザインの授業は初めてでとても刺激になり、今後もいっそう頑張って、もっともっと調理の技術を高めていきたいと感じました。




1月19日(金)、生活デザイン科3年生が校外学習で住宅展示場(プレステージ城東)の見学に行きました。福祉、保育、各類型の視点から現代の住宅におけるユニバーサルデザインを実際に見学することで、住環境に対する知識と理解を深めることができました。
まもなく高校での生活デザインの学習は終わりますが、学んだことを今後の生活に役立てていきたいと思います。
★生徒感想より
見学してみて、階段にも手すりが付いている家と付いていない家、階段と壁の間に隙間があったり、段差を極力なくす工夫がしてあるなどいろんな気づきがありました。収納の工夫や、お風呂→洗濯→そうじ→料理の動作を結ぶ線が最短距離でできるようになっていることなど、驚く発見がありました。また、キッチンからリビングを見通すことができる家が多く、料理をしながらでも子どもの様子を見ることができる間取りになっているところなども親の立場で見ると安心できてよいと思いました。




1月18日(木)、最後の調理実習でビュッフェ形式の実習を行いました。冬休みに考えたレシピで9品作り、ビュッフェランチを楽しみました。
献立は「瀬戸南おこわ、鶏のからあげ、ジャーマンポテトサラダ、オニオンスープ、シーフードピザ、ほうれん草とベーコンのパスタ、餃子2種、チョコチップマフィン、フルーツ白玉」です。みんなで一緒にできる学校での調理実習はこれで最後ですが、これまでに身につけた調理技術を家庭でも生かしていきたいと思います。




1月12日(金)、リビングデザインの時間に中国デザイン専門学校のインテリア・プロダクト科の中川裕志先生の「建築模型講座」の講義を受講し、実習も行いました。
50分の1のスケールで建築模型を作り、インテリアについて学習しました。専門職の方からインテリア・建築デザインについて学ぶことで、住環境に対する知識と理解を深めることができました。1月19日に予定している住宅展示場の見学にもこれらの知識を生かして有意義なものにしたいと思います。




1月11日(木)、3年間の食物分野の学習の集大成として、献立から盛り付けまで、調理選択者23名みんなで考えたおもてなし「会食実習」を実施しました。3年間お世話になった先生方に喜んでいただけるよう、感謝の気持ちを込めて作りました。
31名の先生方が参加してくださり、「おいしかったよ」「3年間で成長したね」と声をかけていただき、とてもうれしかったです。




生活デザイン科福祉類型3年生23名は、岡山県視覚障害者協会の福原先生に社会人講師として「視聴覚障害者について」ご講義をしていただきました。その中で、点字も教えていただき、「炭焼 鯉乃群」のお店の点字メニューを作成する機会をいただきました。
12月26日にお店に持っていかせていただきました。店長の田辺さんからも色々とお話をしていただき、学習したことが必要とされている方のお役に立てることがとてもうれしく感じました。これからも、3年間学習してきたことを忘れずに誰かのために動ける人になれるよう頑張っていきたいと思います。


課題研究の授業で、D&Tファームへ施設見学、講話をしていただきました。
2年生はバナナの苗はもちろん樹も実際に見るのは初めてで、とても興味津々でした。
見学中にバナナの茎を切り落とし、5分ほど話をしたあとにバナナを見ると・・・。
なんと!もうすでに少し茎が成長をしていたのです!!
バナナの生命力の強さを間近で見ることが出来、また、熱く語ってくださる講師の方の話を真剣に聞き、「学校でもバナナを作りたい」と最後に言ってきました。
今後も積極的にいろんな果樹を学んでいきたいです。



バナナの苗 約15,000鉢のバナナ ハウスに育つバナナ
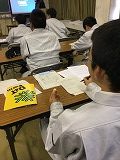
 →
→ 
学校で講話 切ったバナナの茎 5分後には少し・・・!?
「食品製造」の授業で、モモの規格外品を利用してモモ牛丼を製造しました。
1学期は瀬戸南産の卵を使ったプリンを製造。
2学期は包装容器や食品衛生の授業を行い、知識を深めた上で製造実習につなげました。
作った牛丼はレトルト容器に入れて、真空包装。
3年生も楽しそうに取り組みました。
3学期の試食会が楽しみです!




分量決めから・・・ 実習の様子 肉をほぐします! 二重釜を使用して・・・



いい香り~♪ 充てんまでしました! 真空包装中!
12月18日(月)のお稽古で、クリスマスのアレンジメントに挑戦しました。スギのクリスマスをシンボルツリーを中心に、ピンク色のスプレーバラやガーベラでかわいらしくまとめました。サンタクロースとスノーマンの飾りを添えて、完成です!

