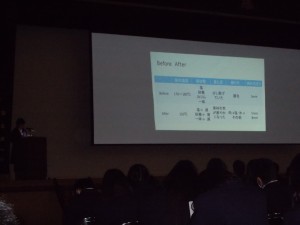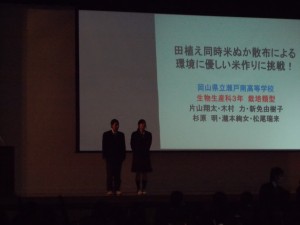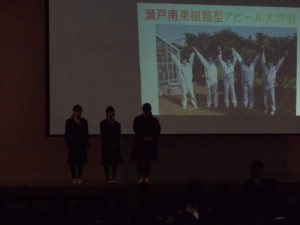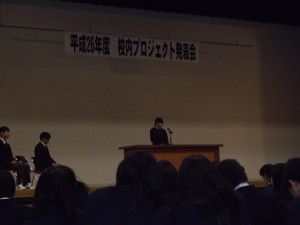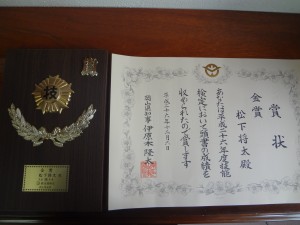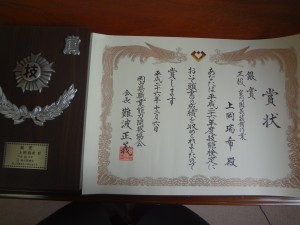1月22日、農業クラブと家庭クラブが合同で『校内プロジェクト発表会』を開催しました。
生物生産科は「栽培類型」と「飼育類型」から2題、園芸科学科は「果樹類型」、「野菜類型」、「草花類型」から3題、生活デザイン科はスクールプロジェクト、そして模範発表として、農業大学校から本校卒業生による卒論研究の計7題の発表がありました。
生物生産科(栽培類型)は、田植えと同時に米ぬかを水田に散布し、無農薬で除草効果を高める取り組みについての研究でした。
生物生産科(飼育類型)は、普通なら捨てられる廃鶏肉を美味しい物に加工して、さらに商品化できないかの検討についての研究でした。
園芸科学科(果樹類型)は、ブドウやモモ、ビワ、カキの栽培方法、PR方法の検討、卒業した中学校への訪問販売の成果などについての発表でした。
園芸科学科(野菜類型)は、根の生育制限など植物に高いストレスを与える栽培法によるトマトの高品質を目指した研究でした。
園芸科学科(草花類型)は、本校独自のオリジナルシクラメンの開発を通して、地域にシクラメンを広げていくという内容でした。
生活デザイン科(スクールプロジェクト)は、エコな学校生活を送ることをテーマに、家庭クラブで行っている環境に配慮したさまざまな取り組みについて発表していました。
農業大学校は、バラの栽培についての高度な栽培管理技術の研究でした。
それぞれの専攻(類型)の取り組みを聞くことで、他学科の学びを知る大事な機会でした。