6月24日(水)の3・4時間目に生活デザイン科1年生40名が調理実習を行いました。この日の献立は、「親子丼、豆腐とえのきだけのすまし汁、野菜のごま酢和え」でした。
材料のお米、玉ねぎ、卵は本校の生物生産科の生産物なので、とても新鮮で美味しい親子丼になりました。また一番だし、二番だしの取り方も、一度実習を行っていた成果もあり、班で協力をしながら調理ができ、実りある実習となりました。
6月24日(水)の3・4時間目に生活デザイン科1年生40名が調理実習を行いました。この日の献立は、「親子丼、豆腐とえのきだけのすまし汁、野菜のごま酢和え」でした。
材料のお米、玉ねぎ、卵は本校の生物生産科の生産物なので、とても新鮮で美味しい親子丼になりました。また一番だし、二番だしの取り方も、一度実習を行っていた成果もあり、班で協力をしながら調理ができ、実りある実習となりました。
野菜栽培の基礎知識を学ぶ教材として「エダマメ」の栽培プロジェクト学習を1年生は展開しています。今日は、3週間前に種まきしたエダマメを生育具合をスケッチしたり、自分がまいた種がどれぐらいの発芽率かを調査・計算しました。今日の目的は、エダマメの葉や茎のスケッチすることにより性質や特徴を理解することに目的としています。なにげなく生えている葉の生え方にも特徴があり、それぞれが分類されていることに感心する生徒もいました。



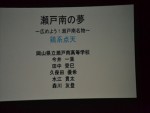

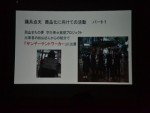
生物生産科の恒例行事、泥んこバレーが6月22日に開催されまが、もうすでに準備が始まっています。まだ田んぼに水も入っていないのにと思われるかもしれませんが、これも恒例の準備風景です。学校で取れる食材をフルに使って、泥んこバレー終了後の炊き出し、味噌汁の具材の準備です。肉団子(親鳥の肉をミンチにして作ります)を「食品製造」の授業で製造します。写真は生物生産科3年生の授業風景です。ミンチにして、サイレントカッターで練ります。その後、大きさを整えて団子に整形していきます。当日まで冷凍保存です。泥んこバレー当日、至福の一杯になればと思い製造しました。最後に瀬戸南産の味噌、ジャガイモ、タマネギを加えれば、至福の一杯へと・・・?!






岡山県学校農業クラブ連盟プロジェクト発表会(食料・生産)に出場する生物生産科 加工班、発表前日にもかかわらず鶏系点天の製造中です。『発表準備ですか~??』
『発表準備です!!』『その答えは??』『発表会の時に。』だそうです。鶏系点天を揚げながら発表練習しているとのこと。頑張っている姿が見えるのはいいことです。頑張れ加工班。






6月16日(火)に、保育類型2年生(女子20名、男子2名)が万富保育園を訪問し、保育園見学実習を行いました。「おたのしみ会」では、振りをつけて歌ったり、大型のペープサート(絵人形劇)を演じたり、ハンドベルの演奏を披露したりしました。
各クラスを見学させていただき、子どもたちの様子をしっかりと観察できたのはもちろん、園の先生方の対応から学ばせていただくことが多く、たくさんの気づきがある実習となりました。
6月3日、岡山県農林水産総合センター畜産研究所で行われた家畜審査競技乳牛の部において、生物生産科3年 水江貫太君が個人の部において140点満点中 128点で最優秀賞を受賞しました。
また、団体の部でも最優秀賞を受賞することができました。団体の部は各校6名の出場選手内、上位3名の合計点で決定いします。生物生産科3年の水江貫太君、大槻琴音さん、井上光君の3名が受賞対象者となりました。さすが3年生というところです。乳牛は本校では飼育していませんが、動画サイトと資料での勉強の結果です。受賞おめでとうございます。




6月16日に生物生産科1年生40人で、約500羽の家移りを実施しました。
1人1羽づつ平飼いの大すう舎からニワトリを捕まえて ケージ飼いの成鶏舎に入れていきます。このニワトリは、1月27日に入すうして育てたニワトリです。これから1年6ヶ月で約600個の卵を産みます。生徒たちは、最初は、おっかなビックリでニワトリを運んでいましたが、慣れてくるのか1人で50羽運んだ人もいました。



本日の実習は、生後3~4ヶ月の雄子牛2頭の去勢実習です。
まず、頭絡を付けます。保定するために横臥保定で牛を転ばせてから4本の足をロープで縛り、保定です。
保定後、メスで睾丸を切開してから精巣が見えるようになってお手製のフックに精巣をかけて電動ドリルでねじ切り、患部を消毒して去勢の完了です。牛のかなりグロッキー状態です。でも、美味しい高級和牛肉生産には欠かせない実習です。実際に自分達で体験した実習は、忘れられないいい体験です。






6月5日(金)井原高校南校地で行われた、学校農業クラブ連盟のフラワーアレンジメント競技岡山県大会に出場し、本校の園芸科学科草花類型の3年生、森脇遥花さんと若本勇気君が優秀賞に入賞しました。
この大会は、岡山県内の農業系高校7校から、14名が参加し、35分間で花束やリボンをつくる実技と基礎的な知識を問うテストなどの合計点で競いました。
この入賞は二人にとって、とても自信になりました。




5月29日(金)に、保育類型3年生(女子19名、男子1名)が岡山市万富保育園を訪問し、保育園体験実習を行いました。生徒たちは、それぞれのクラスで、準備していった造形遊びや絵本の読み聞かせなどで園児とふれあいました。
お絵かきや輪投げ、新聞紙を使ったゲーム、魚釣りゲームなど、準備していった遊びを展開する中で、子どもの心身の発達について、理解を深めることができ、有意義な実習となりました。
6月4日、朝8:40にかわいい子ウシが誕生しました。
お母さんは「さわはやふく」。今回が二回目の出産です。
体重は28Kg。メスでした。
誕生後1時間後には、足を踏ん張って立ち上がり、お母さんのお乳をおなかいっぱいになるまで飲んでいました。
大きく育ってね。

江西小学校2年生と本校園芸科学科3年野菜類型生徒が交流を行いました。本校のイモ畑に、一緒にサツマイモの苗を植えました。本校生徒が苗の植え方を絵を描いて説明しました。その後、小学生数人に本校生徒一人がついて実際に苗の植え方を指導しました。あいにく雨の中での作業になりましたが、小学生たちは目を輝かせながら苗を植えていました。高校生たちも年齢の違う小学生の対応にとまどいながらも楽しい時間を共有でき、充実した交流になりました。



先週からトマトが収穫出来るようになりました。熟れた真っ赤なトマトは光に当たってさらにおいしそうに輝いています。生徒は嬉しそうにトマトを収穫していました。まだ、収穫始めでトマトを収穫できない生徒もおり、羨ましそうにトマトが入ったカゴを眺めていました。




答えは・・・「ジャガイモ」です。
ナス科の植物なので、同じナス科の「ナス」「トマト」などと同じような花ですが、白色の花が房状に着きます。畑一面に花が咲くと、意外ときれいです。
今、生物生産科の栽培コース2,3年生が植えたジャガイモの花が満開になっています。
品種は「デジマ」です(長崎県の出島が品種名の由来です)。
肉質はやや粉質です。
6月中旬頃には、収穫・販売予定です。
煮物、味噌汁、揚げジャガ、ポテトサラダなどに調理して味わってみませんか?
水曜日に開催される瀬戸南市(せとみなみいち)でも販売を予定しています。


5月20日(水)IPU(環太平洋大学)において、本校草花類型生13名とIPUのソフトボール部40名で、花植え交流を行いました。3年前も同じ時期に行いました。今回はサルビア、マリーゴールドといった夏の定番の花です。IPUの学生の皆さんはとても優しくて、緊張していた高校生にはとてもありがたかったです。今まで、小学生や高齢者の方との交流は経験がありますが、大学生との交流はとてもよい経験になりました。



5/24(日)岡山市北区中之町(天満屋北)商店街で行われたSUNDAY TENT WORKERに生物生産科 加工班が、瀬戸南名物 ”鶏系点天(けいけいてんてん)” の試食販売を実施してきました。この参加については、きび日本ビジネスサポート協同組合の松山様の紹介で、「SUNDAY TENT WORKERの出店をしてはどうか? そこで企業の方にアピールしてみては」 との呼びかけに加工班5名の生徒取り組むこととなり参加を決定しました。そして生物生産科の食品製造の授業等を使って2日間がかりで製造した ”鶏系点天” 173個完売することができました。お買い上げありがとうございました。また、松山様のご指導でFacebookの登録とFacebookでのビジネス活動についてレクチャーしていただいたことで、多くのつながりを持つことができ、完売にたどりつけたのとも思います。Facebook友達の方々、ご協力ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。







5月1日(金)園芸科学科1年B・C組の2班は草花の実習でした。用水路沿いの花壇にサルビア(コクシネアとスプレンデンス)の2品種を丁寧に定植(植え付け)ました。サルビアはシソ科の植物で花言葉が「家族愛」。この他、秋まで楽しめ「花壇花」です。「2列以上は千鳥植え」という知識と技術が身につきました。


5月8日(金)には園芸科学科1年B組の1班は中庭の花壇3つにサルビアスプレンデンスを約200株定植しました。草花が最も元気に咲く季節。来週も花壇・プランタなどの花の衣替えが続きます。


本校へ来て下さった皆様ありがとうございました。晴天にも恵まれ、例年より多くの方に来ていただきました。生徒も張り切ってそれぞれの担当をしてくれました。次は12月5日にシクラメンを中心に販売する「シクラメン祭」を予定しています。よろしくお願いします。




暑さを感じる季節になり、校内には様々な花が次々に咲いています。
果樹園のリンゴの花や花壇のラベンダーに昆虫たちが訪れて、蜜や花粉を集めているようです。
花の咲いている短い間に懸命に働いている姿を見ることができ、私たちも頑張ろうという気持ちがわいてきました。勉強、実習、部活動・・・がんばるぞー!



