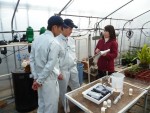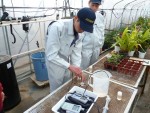2月22日(月)に生活デザイン科1年40名が、「家庭基礎」の授業で針供養を行いました。折れた針や曲がって使えなくなった針を集めて、とうふやこんにゃくに刺し、供養しました。針に感謝の気持ちをこめ、裁縫の上達を祈りました。
カテゴリー別アーカイブ: 各学科
卒業生にコサージのプレゼント
2月5日3・4限目、草花実習室で1年生草花類型生が卒業式に向けてコサージ用リボン作成に取り組みました。
前週からリボン作成に取り組み、恒例にしている2年生から1年生への実技指導を行いました。
2年生6人は照れもありましたが、「リボンのループはこう持てばいいよ」「リボンをねじる時は親指と人差し指をつけたままで少しずらせばいい」等、次第に作るうえでのポイントをタイミングよく指導できました。コツを忘れないように、3本ずつ持ち帰りの宿題としました。




2月29日には、明日の卒業日に備えて、1・2年生で植物(シンビジウム、カーネーション、カスミソウ、レザーファン、ミリオン)を適切な長さに準備したものを組み仕上げて、コサージを作製しました。






卒業式当日、草花類型の生徒から卒業生に出来上がったコサージをプレゼントしました。中には、弟や妹からのプレゼントになった生徒もいて、照れくさそうにコサージをてつけ付けてもらっていました。



その後3年生は、下級生からそれぞれの思いのこもったコサージを胸に、卒業式に臨みました。
かわいい! ヤギ、出産ラッシュ!
2月に入り、ヤギの出産が続いています。ヤギは季節繁殖動物(子どもを産む季節が決まっている動物)なので、ちょうどこの時期がお産に当たります。とてもかわいらしい子ヤギが誕生し、農場はにぎやかです。担当の生徒たちは、母ヤギの愛情に負けないくらい、毎日の管理を頑張っています。

保育講習会(対象:生活デザイン科保育類型2年生)
2月3日に、Tsushima.J(つしまジェイ、金重 恵子代表)の皆さんをお迎えし、保育講習会を実施しました。いきいきと表現する楽しさや、活動に音楽を取り入れることの効果、演じる側と見る側との相互交流があることの素晴らしさなどを体感できる講習会となりました。
生徒感想より:赤ずきんちゃんの劇を見せていただきましたが、動作やセリフなど子どもでも理解できるように、また飽きないように構成されていて、私たち高校生が見てもとても面白かったです。演じたみなさんは、赤ずきんちゃんの物語に出てくる登場人物のイメージにとても合っていて演技も上手でした。パネルシアターは横でピアノの演奏があり、歌を歌ったり、手拍子をしたりして、演じる側も見る側も、みんなが一緒に楽しめる構成なのもいいなと思いました。最後の体を動かす遊びも、人見知りなどでまわりになじめない子どもがいてもみんな仲良く楽しむことができるし、運動が苦手な子も体を動かすことが楽しいなと思える内容でした。いろいろな工夫や子どもたちが楽しめるようなはたらきかけがあって、お手本にしたいことばかりでした。今回の講習で学んだことを次の実習などにいかして頑張りたいです。
美味しいトマトプロジェクト2 ~園芸科学科~
今回は1年生が先月末に種をまいたトマトをポリポットへ鉢上げしました。この作業は、茎や葉が成長するにつれて根の量も増えてくるので根が広がりやすいポリポットに移しかえて、トマトにとってよい環境にするのが目的です。生徒は大きくなったといってもまだまだ小さいトマトを説明通り丁寧に移し替えていました。この状態で定植前まで大きくします。しっかり管理していい苗にしましょう。



生活デザイン科1年最後の実習!
2月9日(火)に生活デザイン科1年40名が、「フードデザイン」の授業で最後の実習を行いました。この日の献立は、「ケーキ寿司 なめこ汁 いちご大福」でした。ケーキ寿司が出来た瞬間、どの班からも歓声や拍手が上がりました。
調理実習が好きで、毎回とても楽しみにしていたクラスだったので、最後の実習は寂しいですが、2年生でもさらに技術が上達できるよう頑張っていきたいと思います。
味噌の仕込み 無事終了!
毎年好評の生物生産科の味噌。今年も仕込みが無事終了しました。本校で育てた米と地元産の大豆、そして麹(こうじ)菌と塩と水だけでつくる無添加の米味噌です。栽培類型専攻の3年生から2年生、1年生へと、伝統の味が引き継がれました。来年度の10月頃から校内で販売予定です。よろしくお願いいたします。



1年生、初めてのデビーク(断し)
1月26日に入すうしたヒナをデビーク(断し)しました。初めての体験です。先生の手本を基にヒナの保定をし、デビーカーでくちばしの先のとがった部分を少し焼きます。尻つつきの防止のためです。全部で550羽、「総合実習2時間の間でできるかなぁ。」「痛くないのかなぁ。」かわいそうの気持ちを捨てて頑張りました。何度か経験するごとに上手くなりました。2時間で全部できて達成感一杯です。尻つつきなんかしないで、みんなで大きく育て!!
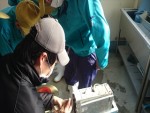





生活デザイン科1年!料理講習会
2月3日(火)生活デザイン科1年40名「フードデザイン」の授業で、外部講師授業がありました。今回は、みかしほ学園日本調理製菓専門学校の酒井宏純先生・青木香織先生に「鶏肉の照り焼き 高野豆腐の卵とじ 菊花大根 白和え」をご指導いただきました。

お弁当を作る時には、「五味・五色・五法」が大切であること、段取りをよくして実習を始めること、包丁の扱い方など生徒達は熱心に講義を受けた後、実習に取り組みました。どれもとても美味しくてお腹いっぱいになりました。
生活デザイン科3年テーブルマナー講習会
2月1日(月)、ANAクラウンプラザホテル岡山にて西洋料理のテーブルマナー講習会を行いました。
テーブルに着いた後、マナーについての説明を講師の細谷さんからお聞きしながら、フルコースのお料理を美味しくいただきました。
初めは緊張していましたが、次第に慣れてきて、楽しい雰囲気で講習会を受けることが出来、とても勉強になりました。
視覚障害者・盲導犬講習会
1月28日(木) 視覚障害者 岡崎起惠子氏と盲導犬リーアムをお招きし、本校生活デザイン科1年生を対象に「視覚障害者・盲導犬講習会」を実施しました。
以下、受講した生徒の感想を紹介します。
・視覚障害者の方と盲導犬に実際に会ってみたのは、初めてです。だから最初は反応に困ったけれど、岡崎先生はとても明るい人で、リーアムは本当に賢くてすごいと思いました。また、盲導犬の仕事、一つ目は障害物をよける、二つ目は段差を教える、三つ目は曲がり角を教えるという3つの仕事があるということが分かりました。
・岡崎先生がパソコンで本を読んだり、パソコンから聞こえる音で聞き取っているのがすごいと思いました。
・岡崎先生が家で1人で料理を作ったり、コーヒーをいれたりしているのはすごいと思いました。先生が編み物ができないのは、目が見えないからではなく、苦手なだけだからと言われたのが印象に残りました。
ビジネスマナー講座の実施(2回目)
1月28日(木)、先週に引き続き、株式会社ラーンズより営業開発課所属の中川公美子先生にお越しいただき、本校の生活デザイン科1年生を対象に「ビジネスマナー講座」を実施しました。以下、受講した生徒の感想を紹介します。
Hさん:2回にわたって基本的なマナーを教えていただき、とても良い経験になりました。お盆や茶托を使った正しいお茶の出し方が特に勉強になりました。卒業式で来賓の方にお茶をお出しする機会があるので今日学んだことを思い出して実践したいと思います。金封の知識は家に帰って母に話すと、母も知らないことがあり、家族にも役立ちました。
Sさん:友達と敬語で話し合うことやビジネスマナーについて考えることは、普段は少ないので、とても勉強になりました。挨拶の「拶」の漢字の上の「く」の部分がお辞儀を表していることを知り、深いなと思いました。今までに習って知っていたことも、なぜこうするのか、なぜこうしなければならないのかをより詳しく知ることができ、とてもよい時間だったと思いました。
トマトの種をまきました ~園芸科学科~
1年生野菜類型専攻生が来年度栽培用ハウストマトの種をまきました。品種名は「麗夏」、大玉で美味しく「王様トマト」とも言われています。このトマトは、自分達の栽培教材として半年間育てていきます。その間に、支柱を立てたり、誘引、芽かき、収穫や対面販売など色々な実習を体験・学習します。今日は、野菜をよく見に行くことがよい野菜を育てるために必要なことも学びました。美味しいトマトをみんなで作りたいと思います。



保育園体験実習(保育類型2年生)
1月27日(水)に、生活デザイン科保育類型2年生21名(女子19名、男子2名)が万富保育園を訪問し、保育園体験実習を行いました。今回は、どの班も手作りのパネルシアターを準備し、園児の前でお話を演じました。 また、午後まで実習をさせていただいたので、園児たちと一緒にお昼ご飯を食べたり、パジャマへの着替えを手伝ったり、ゆっくり交流する時間があり、お昼寝の様子などを見ることもできました。
写真①パネルシアター「はらぺこあおむし」の様子です。『すみれ組さん(3歳児クラス)で演じました。何個も果物が出てくるところでは一緒に数をかぞえてくれたり、最後に大きなちょうちょが出てくる場面では「うわ~きれい」「にこってしとる」など良い反応をもらえました。あおむしが食べる時には「むしゃむしゃ」と言ってくれたり、楽しんでもらうことができました。』(生徒感想より)
写真②パネルシアター「どうぞのいす」の様子です。ちゅうりっぷ組さん(2歳児クラス)で演じました。
写真③ゆり組さん(5歳児クラス)でプレゼントした手作りのカードです。節分にちなみ、鬼の折り紙を貼ってメッセージを書いています。
調理実習!今日は和食です☆
1月27日3・4限目に生活デザイン科1年が、「フードデザイン」の科目で調理実習をしました。今日は、和食で「鯖の味噌煮 かぼちゃのそぼろあんかけ けんちん汁」を調理しました。
日頃、鯖を調理しない生徒たちも、一口食べると「おいしい~!」と笑顔で話していました。だし汁も一番だしの昆布とかつおぶしから取り、だしのうま味も味わえた実習でした。寒い日々が続く中、調理室はおいしい笑顔で温かい雰囲気に包まれた時間となりました。
「絵本の読み聞かせ講習会」
1月21日(木)に、生活デザイン科保育類型2年生21名(女子19名、男子2名)が積み木の会の方々による「絵本の読み聞かせ講習会」を受講しました。
子どもに絵本を読み聞かせることで、子どもの世界や想像力を広げることができます。また、読み手からの愛情を感じることができ、子どもの情緒の安定や心の発達につながることもわかりました。読み聞かせの技術を高めるための発声練習やイントネーションなども演習しながら教わりました。手作りのパネルシアターや大型紙芝居、手遊びを実演していただき、子どもとの関わり方や保育実習のヒントをいただきました。
シクラメン交配実験をしました。
総合実習で園芸科学科1年生草花類型選択者23名がシクラメンの交配実験を行いました。手順は次の通りです。
○○①蕾(つぼみ)の先が開いたものは全部抜き取り、閉じたものを3つ選ぶ。
○○②蕾(つぼみ)の萼(がく)を持ち、花弁を上下に動かし、花弁とおしべを取り除く(除雄という)。
○○③目的以外の花粉と交配しないように、花にお茶パックを掛ける。
○○④除雄して1週間たっためしべの柱頭に目的の花の花粉をつける(人工交配という)。
○○○目的の花を3種類選び、交配した花からお茶パックを掛ける。
手順が分かると22品種の中から3品種の花を選んで人工交配しました。
ここでの交配実験が成功した花は今年の6月に採種できます。11月に、は種(種まき)をして来年(29年)4月頃、ポット上げを行い、11~12月頃には、自分だけのオリジナルシクラメンが開花する予定です。




いのちの教育 飼育類型編
生物生産科飼育類型の2年生は、肉用若鶏(ブロイラー)の飼育に取り組みました。
昨年の11月11日にヒナを岡山市内の福田種鶏場から導入し、飼育が開始されました。
学校到着後、35℃に保温された部屋に移され、えづけ(飲水、給餌)を行いました。
その後、日常の管理として、エサやり、掃除、ワクチン接種などを行いました。体重測定も毎日行いましたが、その増体量にはビックリ。同じ鶏である採卵鶏(卵を採るための鶏)と比べてみると、驚くほどの差でした。
そして飼育期間が2ヵ月を過ぎ、いよいよ肉として利用するときが迫ってきました。毎日愛情を込めて飼育した鶏たちの命をいただく日が来ました。授業に取り組んだ21名の生徒たちはそれぞれの思いでその実習に臨みました。
「普段何気なく食べている食材がどういう過程で生産され、利用されているのか」、飼育類型でしか学べない「いのちの教育」にふれられたことは私たちの大きな財産になりました。





類型発表会がありました!
1月25日(月)4限目に3年生類型発表会がありました。2年間の福祉、保育類型に分かれて学習してきた成果を1年生対象に発表しました。
3年生は2年間、保育園や福祉施設等での実習や外部講師授業が多くあり、専門科でしか経験できないことを学んできました。机上だけでは経験できない学習を活かして福祉系、保育系へ就職・進学、コミュニケーション力・問題解決力を身につけて、調理系・被服系・情報系へ進学等自分の夢に向かって頑張りました。
1年生にとって、 3年生の発表はとても頼もしく、3年間の成長を感じることができました。
高大連携による研究会及び現場実習を行いました。
平成28年1月14日(木) 岡山大学農学部において、作物開花制御学 教授 吉田 裕一 ・ 後藤 丹十郎先生を講師として、園芸学について学習しました。バイオテクノロジーを活用して植物を生産する研究について、園芸科学科2年生2名・1年生3名と生物生産科1年生1名が参加し、高校では学べない高度な農学技術に携わることができました。この体験を今後の学習に生かしていこうと思います。