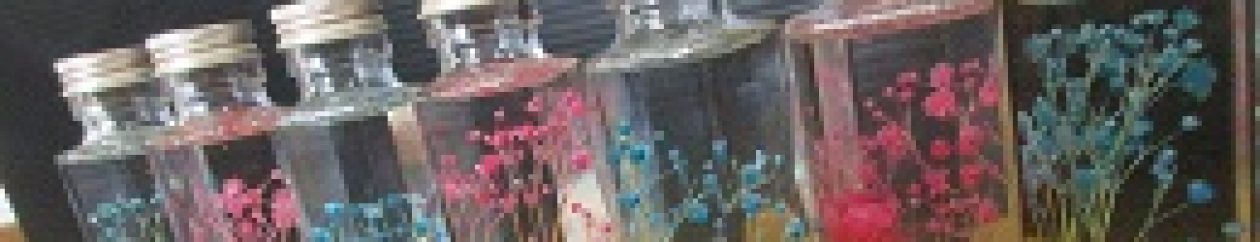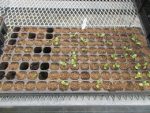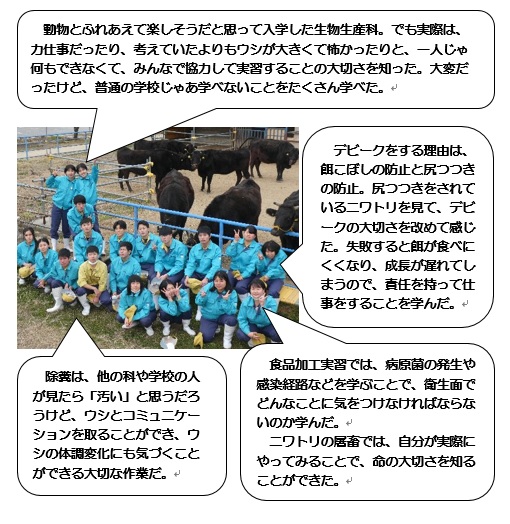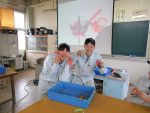2月7日(金)。今年は卒業式が3月1日の日曜日なので、前日の土曜日は休校です。そのため、コサージを28日の金曜日に完成させてから当日までの2日間、鮮度を維持しなければなりません。そこで、今回はステムティッシュを使用したカスミソウのパーツ作りにしっかりと取り組みました。説明の後、花材の切り込み、2~3本の又を合わせたワイヤかけ、ステムティシュの巻き方の練習、最後のテーピングまで、全員で練習しました。
また、来週は特別入試、再来週は学年末考査と練習の時間が取れないので、少しでも感覚を覚えていてもらうため、今まで行ってきたパーツの一つであるリボンを渡し、コサージ用のリボンを作製してくることを課題にしました。本番まであと少し。かわいくてきれいなコサージができるように、みんなで頑張っていきましょう!