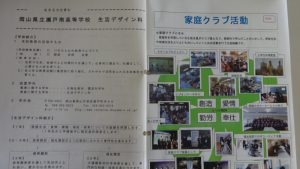4月21日(土) 恒例の「春の苗もの販売会」を開催しました。朝早くから地元の方が大勢来校してくださり、大盛況となりました。お買い上げありがとうございました。
この日のために2月から苗を育ててきた生徒たちは、「ちょっとさびしい・・・」と、まるで娘を嫁に出す親のような思いになっていました。
今後も、いろいろな生産物を「瀬戸南市」で販売していく予定です。こちらもよろしくお願いいたします。
瀬戸南市 開催予定日
5/9、6/6、13、27、10/31、11/28 (14:00~14:30)
8/13、15、17 (13:30~14:00)