4月23日(火)、園芸科学科果樹類型3年の6名が、「課題研究」の授業で昨年に引き続きパスクラサンについて研究を開始しました。
今日は、生産者の福島さんのほ場を見学させてもらい、初めてナシの花を見ることができました。そして、パスクラサン栽培や経営についていろいろなお話をうかがうことができました。今年度は、加工品の開発を赤磐市の方々とタッグを組んで研究する予定です。赤磐市特産のパスクラサンの知名度を少しでも上げることができるように、いろいろ考えて試してみたいと思っています。









4月23日(火)、園芸科学科果樹類型3年の6名が、「課題研究」の授業で昨年に引き続きパスクラサンについて研究を開始しました。
今日は、生産者の福島さんのほ場を見学させてもらい、初めてナシの花を見ることができました。そして、パスクラサン栽培や経営についていろいろなお話をうかがうことができました。今年度は、加工品の開発を赤磐市の方々とタッグを組んで研究する予定です。赤磐市特産のパスクラサンの知名度を少しでも上げることができるように、いろいろ考えて試してみたいと思っています。









4月23日(水)。3月末に水耕施設に植えたメロンを、園芸科学科野菜類型3年生が今学期初めて管理をしました。今年は花冷えが続いてなかなか茎が伸びず心配していましたが、ようやくここまで生長しました。

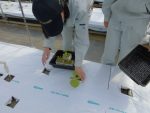
今日の管理実習で、いらない側枝や花を取り除きました。これにより、側枝などにとられていた栄養が主茎に集まるので、株全体がグッと大きくなると思います。5月の連休明けには、雌花への人工交配ができると思います。よいメロンを育てましょう。



4月23日(火)。平成最後の家庭クラブ総会が行われました。
昨年度の行事の報告や、今年度の予定を話し合いました。家庭クラブ員からの質疑応答もあり、みんなで話し合うよい機会となりました。
最後は、役員全員で手話つきで家庭クラブの歌を歌い、有意義な時間となりました。




4月22日(月)。生活デザイン科保育類型3年生が「保育」の授業で、課題で製作した手袋人形を使ってのミニシアター発表会を行いました。歌(童謡)に合わせて指や手を動かしながら、お互いに楽しく真剣に練習の成果を披露することができました。保育園での実習にも持参し、自信をもって子どもたちの前で実演できるよう、練習していく予定です。




4月20日(土)9:30~11:00
「第14回春の苗もの販売会」が晴天の下、本校農場で行われました。
トマト・ナス・キュウリなどの野菜苗を始め、ローストチキン・味噌・卵などの生鮮食品、サルビア・マリーゴールドなどの草花苗、そして本校産の餅米で制作した「おかき」を販売しました。
校長先生のあいさつの後、生徒の元気な「いらっしゃいませ!」から、車で帰られるお客様への「ありがとうございます!!」までの繰り返しが1時間30分間ずっと続きました。
今回は販売物に追加して「おかき戦隊」によるギター演奏「瀬戸南おかき」の校内初披露があり、お客様から手拍子も頂いて盛り上がりました。おいしい麦茶の振る舞いや、ブドウに関するアンケートも実施されました。販売所とは少し離れたところでしたが、動物飼育同好会によるふれあい動物園も大人気でした。幼いお子様とご両親の笑顔がとても印象的でした。
今春入学したばかりの新入生も元気よく参加できました。今年度もお客様に私たちが学んでいる日常の学習成果を発表することができ、大変満足しています。ありがとうございました。










4月19日(金)、生物生産科2年生が用水路の掃除を行いました。農業にとって水は不可欠であり、地域においても大切な資源です。用水路の清掃を通して、地域貢献とともに水の大切さを学ぶことができました。お疲れ様でした。



明日20日(土)の9:30から、春の苗もの販売会を本校の農場で行います。写真は販売前日の野菜苗の様子です。手塩にかけたかわいいわが子(苗)を嫁に出す心境です。
明日、よろしくお願いいたします。





4月18日(木)。暖かくなってきました。温室・ハウスのブドウたちも季節の恩恵をうけ、芽吹き始めています。ブドウは冬の間「休眠」しており、この時期に芽を徐々に吹いてきます。管理作業として、不要な芽を摘み取る「芽かき」を行い、残した芽に栄養分を集中させて充実した枝を作っていきます。これは、吹いてきた芽と花穂の様子です。今後は、生徒たちの様子を順次ホームページで紹介していきます。


4月17日(水)、園芸科学科野菜類型と草花類型の3年生が、今週末20日(土)に行う「第14回春の苗もの販売会」の会場準備を行いました。シートを敷き詰め、テントを15張たて、柱に重りをくくりつけました。これで準備OKです。
野菜類型の生徒は、Oniビジョンの取材も受けました。また、明日の朝刊には広告が入る予定です。ぜひ、お買い物に来てください。



4月14日(日)、生物生産科3年生5名と2年生3名が、真庭郡新庄村で行われた「がいせん桜まつり」で「瀬戸南おかき」を販売しました。
色違いのつなぎを着て「おかき戦隊瀬戸南じゃー」に変身した生徒達が、作詞作曲したオリジナルソングを歌いながら、おかきの販売をしました。「地域との交流と応援」をテーマに活動をしており、パクチーおかきの材料である岡山パクチーの知名度をアンケート調査したり、生のパクチーを見てもらったりもしました。会場となったメルヘンプラザでは、杵での餅つきに参加したり、はやりの歌をギターに合わせて歌うなど、地域の方々としっかり交流することができました。また、つきたてのお餅や、もち米の麺で作ったイノシシチャーシュー入りのラーメンなども頂き、暖かく迎え入れて頂きました。
歴史あるがいせん桜通りの町並みも見学してきました。ラジオや新聞の効果もあり、声をかけてくださった方も何人かいらっしゃいました。ありがとうございました。今後とも「地域の応援隊」として、「瀬戸南じゃー」はおかきの販売をしていきます。






4月8日(月)。始業式のあと、瀬戸南おかきのプロジェクトのメンバーが「おかき戦隊」として活動するためのつなぎを着て、来週14日(日)に新庄村の「がいせん桜まつり」でおかきを販売するときに披露する「おかきの歌」の練習をしました。是非、新庄村まで足を運んでいただき、おかき戦隊の勇姿を見ていただけたらと思います。
なお、山陽新聞の取材も受け、生徒達はおかき販売への意欲を記者に伝えていました。この内容は2~3日後に紙面に掲載される予定です。



瀬戸南高校では、約1,400羽の採卵鶏を飼育して鶏卵を生産しており、生物生産科飼育類型の1・2年生が、春休み中も当番を組んで飼育管理の実習をしています。毎日、鶏舎で卵を集める「集卵」をし、卵を洗って商品にする「洗卵」をします。そして、カキガラの給与や掃除もていねいに行います。毎日決まった管理を確実に行う・・・。生き物を飼育管理する上でとても大切なことです。生徒のみなさん、これからも良品質の鶏卵を生産していきましょう!






今週、園芸科学科野菜類型の1年生が大玉トマト(麗夏)の定植をしました。始めに、植える苗の大きさや植えるときの蕾の向きなど、苗を見るポイントを説明しました。その後、ビニールハウスに入って植え穴を開け、水を入れて、深さに気を付けながら丁寧に苗を植えました。一年生なので、これから成長するトマトの姿をイメージをすることは、まだ難しかったかもしれませんね。しばらくは管理が続きますが、しっかり世話をしておいしいトマトを皆さんに届けましょう。



3月29日(金)、実習でモモを摘雷した後、「フルーツアート」を行いました。これは、まず「どんなフルーツを使用するか」「どんな配置にするか」等を考えて原画を作り、その後、実際にフルーツをカットして盛りつけるという「美的センスを磨く」学習です。今日は、使用できる本校産のフルーツが時期的に無いのでスーパー等で購入しましたが、夏には本校で収穫したフルーツを使用して、再度実施したいと思います。後で味わうこともできるので、生徒は張り切ってアート作品に取り組んでいました。



雨が降ったりやんだりの日々が続いていますが、果樹圃場のモモの蕾が開花し始めました。
3月28日(木)、実習でモモの「人工授粉(じんこうじゅふん)」を行いました。今回は、「大玉白鳳」という品種の花の花粉を、おかやま夢白桃(花粉が無い品種)のすべての花に受粉棒を使って受粉を行いました。岡山特産のモモの良品生産のために、地道な作業がいろいろとありますが、「おいしいモモを収穫し、地域の方に喜んでもらいたい」と、忍耐強くこつこつ実習を進めています。
来週から2年生に進級ですね。頑張っていきましょう!


「おかやま子ども応援推進委員会・地域家庭教育推進部会」主催の「平成30年度 わが家のすこやか日記」に、生活デザイン科3年の宮﨑さん(高島中出身)の作品が掲載されました。これは、夏休みの課題として、生活デザイン科3年生が取り組んだ作文です。母親からもらったCDの音楽に日々励まされたことが、温かい表現で書かれています。おめでとうございます。
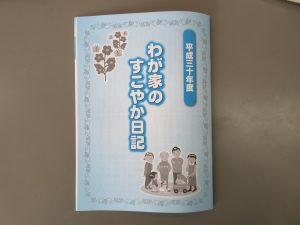
3月26日(火)、生物生産科の「瀬戸南おかき」プロジェクトに取り組んでいるメンバーのうち4名が、「瀬戸南おかき・パクチー」の材料となるパクチーを栽培されている「黄ニラ大使」こと植田輝義さんの圃場にお邪魔して、岡山パクチーの収穫、洗浄、選別、計量、箱詰めの作業を体験しました。機械での出荷箱作りなど学校では体験できない事をしたり、作業での苦労話などを聞くことができました。プロジェクトメンバーで新しく作ったカラフルなつなぎを着て訪問し、楽しく農業体験ができ、植田さんにも大変喜んで頂きました。お忙しい中、ありがとうございました。





3月19日。ストックの八重鑑別を園芸科学科2年生が行いました。ストックは、同じ品種にもかかわらず、種をまくと一重咲きの花の苗と八重咲きの花の苗が約1:1の割合で現れます。2月25日に播種した苗が、現在、本葉がのぞき始めているので、この段階で行える鑑別方法を勉強し、実際にやってみました。残した苗が本当に八重咲きなのか、生長してから確認をします。



八重と一重の花 選別中・・・
3月15日(金)、本校の牛舎で、ウシ(黒毛和種)の「はなゆり号」から受精卵を採取しました。今回は、岡山家畜保健衛生所と岡山県農林水産総合センター畜産研究所のご協力により実施することができました。生物生産科飼育類型の1・2年生は、獣医さんや研究員さんの作業を見学するとともに、実体顕微鏡でウシの受精卵や精子などの生殖細胞を観察しました。とても貴重な経験をすることができました。ありがとうございました。





3月19日(火)、園芸科学科野菜類型の生徒達が販売用の大玉トマト「ホーム桃太郎」の苗をビニルポットに鉢上げしました。鉢上げ作業の目的は、苗を販売できるまでの大きさにするためと、苗の移動などの管理をしやすくするためです。この時期は、ナスやピーマンなどの鉢上げもします。地域の方に喜ばれる苗づくりに毎日励んでいます。

