生物生産科3年生の総合実習で子牛の体重測定を行いました。7月末に生まれた子牛なので、約1か月でどれくらい成長したのか確かめました。生まれたときには47kgでしたが、72kgにまで成長していました。子牛にとっては母牛から離れるのは初めての経験だったので、体重計まで誘導するのがとても大変でした。これからもすくすく健康に育ってほしいです。


生物生産科3年生の総合実習で子牛の体重測定を行いました。7月末に生まれた子牛なので、約1か月でどれくらい成長したのか確かめました。生まれたときには47kgでしたが、72kgにまで成長していました。子牛にとっては母牛から離れるのは初めての経験だったので、体重計まで誘導するのがとても大変でした。これからもすくすく健康に育ってほしいです。


9月4日(水)、岡山県農林水産総合センター畜産研究所を会場に、家畜審査競技(肉用牛の部)が開催されました。家畜審査競技とは、簡単に言うと複数の家畜(今回は黒毛和種)を見比べ、順位付けをする「審査眼」を競う競技、いわば「牛のミスコン」です。結果は残念ながら入賞することはできませんでしたが、他校の様子も知ることができ、良い経験となりました。 今年度は1・2年生が出場したので、来年以降上位入賞できるよう頑張っていきたいと思います。
今回の競技を開催するにあたって、会場と出題家畜を提供していただき、また審査長として講評していただいた岡山県農林水産総合センター畜産研究所の皆様に感謝申し上げます。





9月4日(水)、園芸科学科3年C組の草花類型の生徒がシクラメンの葉組みとリング付けを行いました。まず、温室に入る前によく手を洗い、さらに消毒をしてからシクラメンに触るようにしています。シクラメンは病原菌に弱いため、この先、病気などにかかると大きなダメージを受けるからです。生徒も気が引き締まって一生懸命に取り組みました。
葉組みをすることで、花芽や葉芽がたくさん出てくる箇所(芽点)に光が当たりやすくなります。リングは葉組みをした状態を固定するもので、シクラメン祭に出荷するまであと2回行います。「今年も多くの花が咲きますように・・・。」みんなで頑張っていきます。




9月4日(水)、生物生産科3年の醤油プロジェクトメンバー6名が、近隣の笹埜醤油醸造元で黒大豆醤油の圧搾を行いました。この醤油は、プロジェクトメンバーが1年生の時に学校で栽培した黒大豆を、3月に麦麹と塩と水で仕込み発酵させたものです。もろみを布に広げて袋状に折り畳み、その上にまた布を敷いてもろみを広げていく。この工程を何度も繰り返し、自然に醤油が垂れてくるのをまちます。圧力をかけて搾るのは明日になります。そして、搾った醤油は樽に入れてしばらく寝かせ澱を沈ませます。
搾りたての生醤油の味見もしました。「うどんにそのまま付けたらおいしそう」という意見がありました。 10月に加熱後、瓶詰をして販売する予定です。黒大豆の醤油、楽しみにしていてください。






9月3日(水)、午前7時頃に黒毛和種の子牛(オス)が生まれました。体重は40kgで平均より少し大きい子牛でした。
分娩は午前6時頃から始まり、前肢が出てきてからちょうど1時間程度で終わりました。母子ともに健康で安心しました。元気で立派に成長してくれることを願っています。


9月3日(火)・4日(水)に、赤磐市さんの取り計らいで、果樹類型3年生の地域貢献グループが、「ワイン用ぶどう収穫及びワイン醸造についての学習&パスクラサンフルーツソース勉強会」という名の合宿を課題研究の一環として実現することができました。 一日目。午前中は、キャンベルとリースリングというワイン用ブドウの収穫を体験させていただきました。市役所の方も応援に来てくださいました。午後は、選果場でブドウの傷んだ箇所を取り除く調整作業を行いました。夜は、生産者の方を招いて意見交換会を行いました。生産者の方々の苦労や熱い思いを知るよい機会となりました。
二日目。朝から、パスクラサンのラベルデザインについて話し合いをしました。生産者の方を前面に出そうという案で一致しました。次に、ドイツの森の中にある「是里ワイナリー」で、ブドウを搾汁する工程を見学させていただきました。そして、ワイン製造について沢山学ぶことができました。製品として消費者の方々の手に渡るまでいろいろな工程があり、コストと手間がかなりかかっていることがよくわかりました。
課題研究のまとめに大いに役立つ合宿になりました。ありがとうございました。








8月29日(木)、おかき戦隊せとなんじゃーのメンバー4名が、高梁市吹屋でトウガラシの収穫をしました。天気予報では雨でしたが、作業を始めると奇跡的に雨がほとんど降らず、最後まで収穫作業をすることができました。収穫した約10kgのトウガラシは、吹屋地区にある佐藤紅商店で柚子と塩を混ぜて「柚子胡椒」に加工されます。その柚子胡椒を使った柚子胡椒味のおかきを生産し、10月27日の高梁市のお祭りで販売する予定です。是非、足を運んでみてください。
なお、この日は山陽放送の取材があり、瀬戸南おかきの歌を歌いながら収穫している様子がRSKイブニングニュースで放送されました。山陽放送の方々、ありがとうございました。





8月26日(月)、生物生産科1年生がハクサイの播種を行いました。種子のまき方やポイントなどの説明を受け、セルトレイにハクサイ(品種:黄ごころ75)を播種しました。全員で協力しながら、説明どおりに播種することができました。
翌日には種子から芽が出ていました。9月中旬に定植、11月に収穫する予定で、収穫したハクサイは販売したり、家庭に持ち帰って味わってもらいます。大きく育てるぞ!




8月26日(月)、生物生産科3年生の醤油プロジェクトメンバーのうち3名が、醤油製造を委託している近隣の醤油醸造元に醤油の状態を確認に行きました。この醤油は、学校で育てた黒大豆を材料に、メンバーが1年生の3月に醤油醸造元で仕込み、定期的に状態を確認してきたものです。
今後の予定ですが、9月上旬にもろみを搾って寝かせた後、10月に火入れ(加熱)をして瓶詰めを行います。10月のシクラメン祭で販売できるように、ラベルの作成や販売方法を生徒たちで考えていきます。今年限定の黒大豆醤油、楽しみにしていてください。


8月22日・23日に岡山市役所1階ロビーで行われる「岡山県環境保全型農業推進パネル展」に、生物生産科栽培類型の3年生が課題研究で取り組んでいる「お米甲子園を目指した良食味米生産研究」のメンバーが作成した写真パネルを展示しました。
生物生産科では、「菜の花農法」や「レンゲ農法」といった化学肥料や農薬に頼らない稲作を行ったり、種もみは農薬を使わない「温湯消毒」をしたり、稲作の副産物である稲ワラを牛の餌に利用したり、牛糞を発酵させて肥料として利用したりと、環境保全型農業に取り組んでいます。これらの様子や、田植えから現在までに水田で捕まえた「環境に優しい学校の水田に棲む昆虫や両生類」の写真を展示しました。近くまで寄られましたら、是非パネル展を見に来てください。



台風10号の上陸が予想されるため、15日の販売を中止いたします。従って、販売は8月11日と13日の2日間とさせていただきます。場所は校内のトレーニングルーム前で、時間は13:30からです。よろしくお願いいたします。
8月9日(金)、果樹類型3年生全員でブドウの収穫を行いました。そして、11日の販売会に向けての準備・打ち合わせも行いました。多くの品種や規格ごとの調整方法、ラベル貼り、説明の練習など、内容の濃い実習となりました。皆さん、販売会でお待ちしております。









8月8日(木)。相変わらず暑い日が続いています。
今日から、ついに緑系ブドウの「シャインマスカット」「瀬戸ジャイアンツ」「マスカットオブアレキサンドリア」の収穫を開始しました。まず、糖度計で全ての品種の糖度を確認しました。そして、収穫・調整をおこない、パックや箱に詰めていきました。ここまで長く、そしてたくさんの管理作業を行ってきたので、思いもひとしおです。
【 お知らせ 】 8月11日・13日・15日の13:30から、校内のトレーニングセンター前でブドウの販売会を行います。是非、足をお運びいただいて、私たちが丹精こめて作ったブドウをお買い求めください。 よろしくお願いいたします。













8月7日(水)、広島県庄原市の庄原市民会館で行われた、第39回日本学校農業クラブ中国ブロック連盟大会に、生物生産科2・3年の「おかき戦隊瀬戸南じゃー」のメンバー8人がプロジェクト発表に、園芸科学科2年の平山さんが意見発表に岡山県代表として出場しました。
前日の6日には大会リハーサルが行われ、本番に向け入念な確認を行いました。宿舎に戻ってからも、夜遅くまで最後の仕上げとなる練習や修正を行いました。 最優秀賞を目指し頑張ってきましたが、結果はプロジェクト発表、意見発表ともに優秀賞でした。
レベルの高い大会に参加できたこと、今まで一生懸命活動にとり組み練習をしてきたことがよい経験となりました。応援、ありがとうございました。






8月2日(金)、高梁市吹屋で「おかき戦隊瀬戸南じゃー」のメンバーの生物生産科3年生4人がトウガラシの栽培管理を行いました。成長して背丈の伸びたトウガラシが台風などで倒れないように、麻ひもを張って支えました。
暑い日ではありましたが、高梁市吹屋は瀬戸南高校と比べ気温が低く、山から涼しい風が吹いてきて作業がしやすかったです。 このトウガラシで柚胡椒を作っている佐藤さんにも大変喜んで頂き、作業後には、山にキノコ狩りに案内してもらいました。おかき戦隊のメンバーも初めての体験ができてよかったです。
10月には柚胡椒を使ったおかきの新作を持って、高梁市の祭りに参加する予定です。





7月31日(水)、「夏のオープンスクール」を開催しました。電車のトラブルもあり、時間通りに開始できるのか心配されましたが、生徒会役員を中心に、農クと家クが協力して運営にかかわってくれ、無事に終えることができました。ありがとうございました。中学生の皆さん、次回のオープンスクールは10月19日(土)です。
















先日、春作の水耕メロンの片付けをして、今日、生徒が秋作メロンの種まきをしました。今回は赤肉系のメロンを育てます。生徒も春作に続いて2回目になると手つきも良く、メロンの種を発芽しやすくするロックウールの表面処理など手際よくしました。春作は天候にも恵まれて美味しいメロンを作ることが出来ました。でも、交配に失敗したり、収穫前に病気が発生してメロンが出来ない株もありました。秋作は、暑い時期から栽培が始まるので春作より難しいです。頑張って管理をしていきましょう。


5月の連休明けに人工交配した春作メロンを7月の中旬に収穫しました。収穫後、果実の重さや果径の調査をし、追熟をさせました。今年のメロンは、良い出来だった昨年の春作と変わらないほどの良い出来となり、校内販売会では、生徒や先生方に喜んで買ってもらえました。秋作も頑張りたいと思います。

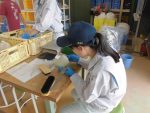

7月26日(金)、生物生産科栽培類型2年生の実習がありました。毎週イネの生育調査を行っています。イネも大きくなり、茎数も急激に増えてきました。生育調査の後は、野菜の授業で栽培したスイカの収穫を行いました。大きく育ったスイカはとても甘くて美味しかったです。 自分で作ったスイカを家庭にも持って帰ります。これからしばらくの間、実習後に美味しいスイカが食べられるぞ!







7月26日(金)。園芸科学科果樹類型2年生が、夏休みの実習で黒系品種の「藤稔」「ブラックビート」の収穫・調整を行いました。電子秤で計量して、パックと三角袋へラッピングしました。試食すると糖度は16度以上あり、とても甘かったです。今日は午後から校外へも販売に行く予定です。ご購入、よろしくお願いいたします。




